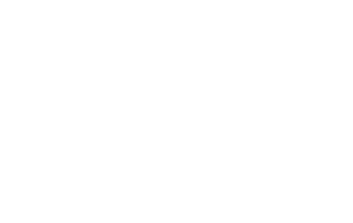歯科における食育とは?口内の健康維持につながる食育について解説
2025/10/20

こんにちは。宇都宮市(雀宮、上三川町)のこうだい歯科です。
生活習慣病の増加やメタボリックシンドローム、過度なダイエット志向、高齢者の低栄養など、食にまつわる問題が多く取りざたされるようになったことで、食育が重要視されるようになりました。
この食育は、歯や口腔の健康とも密接に関連しています。
そこで今回は、食育と歯科の関係性を中心に、口内の健康を維持するための方法について解説します。
食育とは

食育とは、さまざまな体験を通じて食に関する知識を学び、バランスの取れた食事を自ら選ぶ力を養うことを意味しています。
農林水産省では、食育を「生きる上での基本であり、知育、徳育、体育の基礎」と定義しており、文部科学省は「子どもたちが正しい食の知識と望ましい食習慣を身につけること」と説明しています。
食育は、幼少期から高齢期までのライフステージに応じた食事指導を通じて、個々の健康を支え、心豊かな生活を築くための大切な要素として位置づけられています。
歯科と食育の関係性

食育は、栄養バランスや旬の食材の取り入れ方、味わい方など「食べ方」についての重要な知識を育むことを目的としています。
この食べるという行為は口を介して行われるため、健康的に食事を楽しむためには、虫歯や歯周病を予防し、お口の健康をしっかりと維持することが欠かせません。
健全な食生活は、口腔内の健康を守ることにもつながります。
食育と歯の健康において大切なこと
食材の大きさや硬さを工夫する

食材の大きさや硬さを工夫することは、子どもの歯やあごの健康的な発育に欠かせません。
成長段階に応じた適切なやわらかさの食材からスタートし、少しずつ硬さを増していくことで、歯やあごに必要な刺激を与えることができます。
成長に応じてかみごたえのある食材を取り入れることで、歯並びやかみ合わせを促進する良い刺激となります。
栄養バランスのいい食事をとる

子どもの成長に必要な栄養素をバランスよく摂取することは、歯や骨の健康に直結します。
カルシウム、ビタミンD、タンパク質などを十分に摂取できるよう、乳製品や魚、緑黄色野菜をバランスよく食事に取り入れましょう。
反対に、砂糖を多く含むおやつや飲み物は虫歯の原因となるため、回数や量、時間を決めてとるようにしましょう。
左右のあごを使い、よくかんで食べる

ひと口で約15回かむことを目標にすると、歯やあごにバランスよく負荷がかかり、歯並びやかみ合わせが健全に成長しやすくなります。
また、少し硬めのものもかむことで、あごの筋肉が鍛えられます。さらに、左右均等にかむ習慣を身につけることも大切です。
片側だけでかむ癖がつくと、片方の歯に偏った負担がかかり、あごの発育に悪影響を及ぼしたり、顎関節症や歯並び悪化を引き起こしたりしやすくなります。
良い姿勢で食べる
食事の際の姿勢は、歯の健康やかみ合わせに影響を与えます。背筋を伸ばし、足をしっかり地面につけた状態で食事をすることが大切です。
姿勢が崩れた状態で食事をすると、かみ合わせや歯並びに悪影響を与える可能性がありますので、日常的に姿勢を正すことを意識しましょう。
長時間食べ続けない
だらだらと食べ続けないように心がけましょう。
虫歯は一度に食べる量よりも食べる回数に影響されます。
常に口の中に物がある状態だと、酸性状態が続き虫歯のリスクが高まります。
おやつなど甘いものは1日に1回と時間を決め、食べる回数を減らす工夫が必要です。
ライフステージ別の食育と歯の健康
乳児期・離乳期

乳児期・離乳期においては、離乳食を通じて「かむ」「飲み込む」といった機能の発達が促されます。
指を吸ったり、おもちゃをくわえるといった行動は、口唇や舌、あごの動きを促し、食べ物の形や硬さを感じるための準備となりますので、無理に止めないようにしましょう。
幼児期

3歳頃にはさまざまな食べ物をかみ、飲み込む能力が成熟します。
よくかむことを促すために、さまざまなサイズや硬さ、歯ざわりの食べ物を与えるようにしましょう。
また、誤った食べ方や生活習慣は、肥満や健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、常に食習慣を見直し改良していく必要があります。
飲み物で食べ物を流し込む癖や早食い、丸のみが習慣化しないようにしましょう。
また、間食は規則正しくとり、夜食や砂糖を多く含む飲料はとりすぎないように気を付けてください。
小・中学生

この時期は、乳歯が永久歯に生え替わり、永久歯列が完成する時期です。
小学校低学年頃には、上下の第一大臼歯が生え揃い、かむ力が向上しますので、硬さや弾力のある食材をそれまでよりも増やすようにしましょう。
前歯が生え揃う時期は、前歯で食べ物をかみ切り、口に入れられる量を学習できるよう、食べ物を大きめにカットするようにしてみてください。
また、唇をしっかり閉じてかめるように注意することも大切です。
さらに、食事に関するマナーについても少しずつ教えていきましょう。
また、食事に関しては幅広い味覚を体験することが重要です。
外食やお総菜などで食事の選択肢が限られる場合もありますが、甘味や塩味以外に、苦味や辛味、渋味も取り入れることで、偏った味覚嗜好になるリスクが抑えられます。
小学校高学年以降は、塾や部活などで生活習慣が乱れがちにもなりやすいため、間食や夜食の量に気をつけ、できる限り規則正しい食生活になるようにしましょう。
高校生

高校生になると、親知らずを除く永久歯がすべて生え揃います。
それまでの子ども時代に培ったデンタルケア能力に差が出てくる時期でもあり、歯と口腔の健康に個人差が生じやすくなります。
保護者の目が行き届きにくくなる時期のため、定期的な歯科検診を促すなどして口内の健康を維持していけるようサポートしましょう。
まとめ
食物の選び方や食べ方が歯の健康に大きく影響するため、食育を通して健全な食習慣を身につけることは、歯や歯ぐきをはじめとした口内の健康を守ることにもつながります。
食材をよくかんで食べる、さまざまな大きさ、硬さの食べ物を食べる、姿勢を正して食べる、間食を控えるといったことに気を付けることで、食事を楽しみながら、口腔内の健康を維持していきましょう。